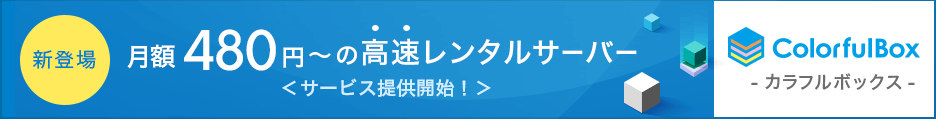
|
From : kennzo yamaoka Date : 2002.11.03 13:28 Sub : ロシアの9・11」ー。 |
「ロシアの9・11」ー。 モスクワの劇場占拠事件でロシア特殊部隊が劇場内に突入した10月二十六日を「コメルサント」紙はこう呼んだ。昨年九月十一日の米中枢同時テロを境に、テロとの闘いが「文明世界の秩序破壊に立ち向かう戦争」と初めて認識され始めたとすれば、今年の十月二十六日はその認識が多くのロシア国民の心中で鮮明な輪郭を成した日だともいえる。 ソ連崩壊十年の節目に米国・経済の中枢がウサマ・ビンラーディン氏のテロ組織アルカーイダに直撃され、その一年余り後に今度はロシアの首都がチェチェン武装勢力に急襲された。アルカーイダとチェチェン武装勢力の関係はなお明確ではないが、米露が相次いでイスラム過激派との「戦争」、換言すれば「国際テロ戦線」からの挑戦に晒された事実は改めて時代の大転換を痛感させる。 特にモスクワの事件では世界の大都市での占拠事件史上、最多の約八百人という人質が取られ、その人質救出にこの種の事件としては初めて特殊ガスが使われ、そのガスによって人質の全犠牲者百十九人(二日現在)の98%以上が死亡したという点に特徴がある。 特殊ガスとは詰まるところ「軍事用秘密科学兵器」の一形態にほかならない。 論議の焦点は当然、特殊ガス使用というプーチン政権の対応の是非、ガス吸引による死者数の多寡という結末に移った。だが、欧米各国政府は犠牲者への深甚なる哀悼の意を表しつつ、プーチン政権の対応と結末のいずれについても一様に賞賛や支持を表明した。 さらにガスの種類をロシア当局が隠し、それが治療を妨げた点を日本を含む世界のマスメディアの多くは批判した。しかし欧米政府には「やむを得ず」の立場が目立ち、顕著な非難や批判は聞かれなかった。日本政府が犠牲者を悼み、テロを非難することにのみ重点を置いたメッセージを送ったのとは対照的である。 英国の著名な安全保障・防衛問題専門家、ポール・ビーバー氏は「米中枢同時テロ後、西側指導者はいや応なく、自国の心臓部で爆発する軍事規模の脅威に直面させられている」(ロンドン発ロイター電)と論じる。「ジェーンズ・ワールド・アーミーズ」のチャールズ・ヘイマン編集長は「今回の事件は、何人殺されたかではなく、何人救出されたかで見るべきだ。ロシアが採った以上の解決策を期待するのはむずかしい。ロシア当局の成分秘匿も将来の犯行を企てるテロリストに手の内を明かさないという意味で正しかった」(同)と指摘した。 ビーバー氏が言う「軍事規模の脅威」とは「戦争」にほかならない。その言葉を敷衍すれば、テロは「戦争」であり、西側諸国の首都は今やいつでもテロ現場という「戦場」に転化しうる脅威に晒され、そうした認識がすでに欧米では定着しつつあるということでもあろう。事件後のプーチン大統領の支持率は「85%」に急上昇したとの世論調査をそのまま信じるなら、ロシア国民の意識改革も一挙に進んだということか。 ロシアからの独立に走るチェチェン武装勢力による今回の事件は、ロシア固有のテロでもあるが、最低これが世界各地のイスラム過激派のテロ行為と相互に影響し合っているのは疑いない。チェチェン紛争はソ連軍のアフガニスタン侵攻の九年間に、まもなく追いつき、年間平均の犠牲者数はソ連がパキスタンや米国を間接的な敵に回したアフガン紛争を上回っている。 チェチェン側のロシアへの増悪は頂点に達し、イスラム同胞の要求に呼応して今回の事件を上回る過激で大規模な「戦場」が世界に現れない保証はない。 「戦場」ではテロリストの要求に決して譲歩せず、同時に無辜の人命を一人でも多く救出するギリギリの近代戦術は日々更新されねばならない。一方で「戦争」である以上、一定の犠牲者が出る覚悟も決めねばならない。われわれはいや応なく、そうした時代に引きずり込まれてしまった事実を今回の事件は示した。 四半世紀前の1997年9月、日本赤軍が日航機をハイジャックしてバングラデシュのダッカに強制着陸させた事件で日本政府は完全譲歩し、乗員・乗客百五十一人の人質と引き換えに日本で在監中の犯人の仲間六人と六百万㌦(当時約十六億円)をダッカに輸送させてしまった。 時代が激変した今、こうしたお人よし解決策は世界のブーイングを呼ぼう。劇場占拠事件は日本にも重い教訓を突きつけている。 |
|
From : 山岡 兼三 Date : 2002.07.21 14:01 Sub : 有事論 |
戦後憲法下に於いて戦争論や有事論は長い間、まともに論じることは許されない題目でした。今日に於いてすら防衛大学校は別として、一般大学の政治経済学部や法学部政治学科に於いて、軍事科学や戦争論が講じられることはありません。あるとしても平和論や平和学に於いて部分的なものにとどまっています。そしてこの平和学においては平和が善であり、戦争は無条件に悪であることが自明の前提とされます。だがこのように勧善懲悪的に割切ることができる程に私たちの置かれた状況は幸せなものであるのかどうか、またそれだけでなく戦時・戦争を考えることによってはじめて平和を具体的に考えることができるのではないか、このような逆説的な現実に我々は取組むのです。 戦争の対概念としては「平和」が通常想定されます。したがって戦争が絶対悪であり、それを予防したければ軍備をなくせばよいというのが最も分かりやすい答えであるということになるでしょう。そうなると当然の帰結として軍事学も戦略論も悪を準備する学であるから有害無益だということになります。今日の一般大学で軍事が学として教授されることがないのもこうした思考が前提にあると考えられるわけです。だが私たちは戦争論なくして平和論は有り得ないし、戦時(有事)の備えなくして平時を享受することはできない、真に平和を欲するのであれば戦時への備え、-有事を考えること-は不可欠であると考えるのです。逆に言えば非武装主義とよばれる非戦主義は真の平和をもたらすことはできないと我々は考えます。なぜでしょうか。いわゆる非戦主義とは平和を犠牲にして戦うことを拒否する見解です。ではそのような非戦主義としての平和主義は何を守るのか、答えは「平和そのもの」ということになるでしょう。平和は何にも優るということになります。しかし平和でありさえすればそれですべて「よい」ということになるのでしょうか。言換えれば平和は究極の善ということになるのでしょうか。確かに我々は平和であることによって多くの善きものや利益を享受することができます。だがこのことは平和は究極の善ではなくて、より高次の善を獲得するために存在するということを示すものといえます。 そうだとすれば真の平和主義とは、平和であることによって追求すべき価値をもっているものでなければならないというべきでしょう。もしこの追求すべき価値を平和主義が見失うのであれば、我々は正義と不正、自由と隷属、繁栄と貧困などを区別できず、平和主義は不正、隷属、貧困といった悪政に仕える侍女に転落することになるでしょう。これに対して価値相対主義者は次にように批判するかもしれません。正義も時代によって移り変わる相対的なものにすぎず、その正しさを論理的に証明することはできない、むしろ絶対的な価値を主張することが戦争の惨禍を引起こすのである、何が正しいかは個人の好きに任せるのが自由な社会であり、それが国家の役割なのであると。確かにこの世の多くの価値や正義は時代と共に変化します。我々もそれを否定することはできません。しかしその内容が何であれ、確かに正義と不正の区分はいかなる時代であっても絶対的に存在しているし、尊厳と隷属の区分そのものが存在することも否定することはできないはずです。常に外国の侵略や内戦に脅かされる社会、いつ政治的な風向きで犯罪者とされるのか分からないような社会、公衆衛生は行届かず、救援物資は役人に横取りされ、人々が飢えや病に苦しむ社会と今日の日本社会との間の価値の差は相対的であり、どちらが善いのか判断できないのでしょうか。そこには明らかに価値の差が見られるはずです。我々は変転極まりないこの世に於いても善と悪という価値の区別を認めないわけにはゆかないのです。 日本が求める平和とは明らかに善き平和でなければならないはずです。平和でありさえすればよいという、平和そのものを自己目的化した平和論はもはや善悪の区別を知らず、倫理を否定することになります。したがって平和が何かの目的によって否定されなければならないとき、我々は何のために、いかなる平和を欲しているのかが初めて明らかになるのです。要するに平和とは戦争という反対概念によってはじめて明らかになるのだといえます。我々は何を追求し、何を守るために戦うべきなのか、これを示すことで我々の平和論はようやく観念論的平和論を排し、具体的な平和論に接近できるのだといえるでしょう。 実際のところ、相対主義者といえども、実は戦時と平時という価値の差を認めているのであり、むしろ平和そのものを絶対的な価値としているのです。それどころか彼らは我々国民が何もしなくても国家は自動的に我々の面倒を見てくれる召使いのようなものだと思いこんでいます。しかしいい気になっている内に彼らは国家の奴隷に転落することになるでしょう。なぜなら彼らはすべての判断と安全を国家に委ねているわけで、こういう人々は専制国家にこそふさわしい国民であるからです。軍事や警察を否定しながら保護されて安楽に生活している「平和主義者」は、国民主権の名の下に自分が主人であるかのように思い込んでいますが、実はいつ追落とされるか分からないかりそめの主人であり、その本質は奴隷であるということができるでしょう。こうしたむしのよい責任無き平和論と「国民主権」が、今日の日本社会の倫理退廃を生み出したことについてもはや説明を要しないでしょう。平和とは我々が主体的に作り出し、維持していくものです。これは反戦デモや署名運動を意味するのではなく、戦時への覚悟と準備をなすことによってはじめて得られるものです。戦時を想わない者の平和論は、戦ってでも守るべき価値を知らないために、簡単に不正や悪につけこまれ、利用されます。いわゆる護憲論者のいう平和主義はこのように無節操で脆弱です。我々はこのような平和主義を断固退け、正しき平和を追求する。 したがって戦時や有事を考えることは決して戦争をいたずらに招き寄せることではなく、むしろ平和を具体化するために欠かすことのできない作業でもあるということです。江戸期の日本人は泰平の世であるにもかかわらず、武道の稽古をし、学歴社会でもないの学問をし、さらに武士は常に死を思うこと(memento mori)を訓練されていました。彼らは常に武具を身近に置き、それを魂とよぶことによって、武器が単なる道具や手段ではなく、いかなる目的で、いかに正しく用いるのか、という価値と共にあることを意識してきました。こうした侍の精神こそが泰平を維持し、列強の植民地化に直ちに対応する能力を培ってきたのではないでしょうか。武士道こそは悪しき平和でなく、善き平和のために戦う気概をもつ精神性をもっていたといえるでしょう。善き平和は戦時や有事を忘れては達成できないものです。 顧れば戦後日本の平和論は、目的なき経済成長路線とこの点でまったく類似の構造をもってきたといえるでしょう。繁栄は我々に多くの善きものを与えてくれる機会を提供するが、一体それによって我々は何を得るべきなのか、この目的はほとんど考えられることはありませんでした。この繁栄が極点に達したとき、人々は目的を探求することよりも手段を価値そのもののと誤認し、数々の見苦しい行ないをしてきました。この意味に於いても我々は精神性を失ってきたといえます。平和そのものも、金銭そのものも究極価値ではありえないにもかかわらず、それを究極価値と誤認し、閉塞状態に陥っているというのが現在の日本です。平和でありさえすればよい、という心情は、金さえあればよいという心情と相通じるものといえましょう。この二つの過ちは戦後民主主義を支えてきた車の両輪といえます。我々は繁栄の意味を知るためには窮乏を知ることが必要であるように、平和の意味を知るために戦時を知り、それへの覚悟をもつことが必要です。それが平和と富とを正しく統一的に方向づけることになるでしょう。 それでは我々は何のために戦うのか、その目的は何か、この問題を一語で答えることができるなら、我々の世界に政治も哲学も必要ないでしょう。形式論やマニュアルはない、ということだけは確かです。これは個人にとっても一生の課題であり、国家にとっても永遠の課題です。しかし我々は江戸期の武士と同様にそれを意識し続けることによってあるべき平和への道筋を考えることができ、いかに生くべきかを考えられるようになるはずです。我々、こうした観点から有事を想定し、準備することによって我が国のある べき道筋と平和を考えなければいけない。 戦後憲法下に於いて戦争論や有事論は長い間、まともに論じることは許されない題目でした。今日に於いてすら防衛大学校は別として、一般大学の政治経済学部や法学部政治学科に於いて、軍事科学や戦争論が講じられることはありません。あるとしても平和論や平和学に於いて部分的なものにとどまっています。そしてこの平和学においては平和が善であり、戦争は無条件に悪であることが自明の前提とされます。だがこのように勧善懲悪的に割切ることができる程に私たちの置かれた状況は幸せなものであるのかどうか、またそれだけでなく戦時・戦争を考えることによってはじめて平和を具体的に考えることができるのではないか、このような逆説的な現実に我々は取組むのです。 戦争の対概念としては「平和」が通常想定されます。したがって戦争が絶対悪であり、それを予防したければ軍備をなくせばよいというのが最も分かりやすい答えであるということになるでしょう。そうなると当然の帰結として軍事学も戦略論も悪を準備する学であるから有害無益だということになります。今日の一般大学で軍事が学として教授されることがないのもこうした思考が前提にあると考えられるわけです。だが私たちは戦争論なくして平和論は有り得ないし、戦時(有事)の備えなくして平時を享受することはできない、真に平和を欲するのであれば戦時への備え、-有事を考えること-は不可欠であると考えるのです。逆に言えば非武装主義とよばれる非戦主義は真の平和をもたらすことはできないと我々は考えます。なぜでしょうか。いわゆる非戦主義とは平和を犠牲にして戦うことを拒否する見解です。ではそのような非戦主義としての平和主義は何を守るのか、答えは「平和そのもの」ということになるでしょう。平和は何にも優るということになります。しかし平和でありさえすればそれですべて「よい」ということになるのでしょうか。言換えれば平和は究極の善ということになるのでしょうか。確かに我々は平和であることによって多くの善きものや利益を享受することができます。だがこのことは平和は究極の善ではなくて、より高次の善を獲得するために存在するということを示すものといえます。 そうだとすれば真の平和主義とは、平和であることによって追求すべき価値をもっているものでなければならないというべきでしょう。もしこの追求すべき価値を平和主義が見失うのであれば、我々は正義と不正、自由と隷属、繁栄と貧困などを区別できず、平和主義は不正、隷属、貧困といった悪政に仕える侍女に転落することになるでしょう。これに対して価値相対主義者は次にように批判するかもしれません。正義も時代によって移り変わる相対的なものにすぎず、その正しさを論理的に証明することはできない、むしろ絶対的な価値を主張することが戦争の惨禍を引起こすのである、何が正しいかは個人の好きに任せるのが自由な社会であり、それが国家の役割なのであると。確かにこの世の多くの価値や正義は時代と共に変化します。我々もそれを否定することはできません。しかしその内容が何であれ、確かに正義と不正の区分はいかなる時代であっても絶対的に存在しているし、尊厳と隷属の区分そのものが存在することも否定することはできないはずです。常に外国の侵略や内戦に脅かされる社会、いつ政治的な風向きで犯罪者とされるのか分からないような社会、公衆衛生は行届かず、救援物資は役人に横取りされ、人々が飢えや病に苦しむ社会と今日の日本社会との間の価値の差は相対的であり、どちらが善いのか判断できないのでしょうか。そこには明らかに価値の差が見られるはずです。我々は変転極まりないこの世に於いても善と悪という価値の区別を認めないわけにはゆかないのです。 日本が求める平和とは明らかに善き平和でなければならないはずです。平和でありさえすればよいという、平和そのものを自己目的化した平和論はもはや善悪の区別を知らず、倫理を否定することになります。したがって平和が何かの目的によって否定されなければならないとき、我々は何のために、いかなる平和を欲しているのかが初めて明らかになるのです。要するに平和とは戦争という反対概念によってはじめて明らかになるのだといえます。我々は何を追求し、何を守るために戦うべきなのか、これを示すことで我々の平和論はようやく観念論的平和論を排し、具体的な平和論に接近できるのだといえるでしょう。 実際のところ、相対主義者といえども、実は戦時と平時という価値の差を認めているのであり、むしろ平和そのものを絶対的な価値としているのです。それどころか彼らは我々国民が何もしなくても国家は自動的に我々の面倒を見てくれる召使いのようなものだと思いこんでいます。しかしいい気になっている内に彼らは国家の奴隷に転落することになるでしょう。なぜなら彼らはすべての判断と安全を国家に委ねているわけで、こういう人々は専制国家にこそふさわしい国民であるからです。軍事や警察を否定しながら保護されて安楽に生活している「平和主義者」は、国民主権の名の下に自分が主人であるかのように思い込んでいますが、実はいつ追落とされるか分からないかりそめの主人であり、その本質は奴隷であるということができるでしょう。こうしたむしのよい責任無き平和論と「国民主権」が、今日の日本社会の倫理退廃を生み出したことについてもはや説明を要しないでしょう。平和とは我々が主体的に作り出し、維持していくものです。これは反戦デモや署名運動を意味するのではなく、戦時への覚悟と準備をなすことによってはじめて得られるものです。戦時を想わない者の平和論は、戦ってでも守るべき価値を知らないために、簡単に不正や悪につけこまれ、利用されます。いわゆる護憲論者のいう平和主義はこのように無節操で脆弱です。我々はこのような平和主義を断固退け、正しき平和を追求する。 したがって戦時や有事を考えることは決して戦争をいたずらに招き寄せることではなく、むしろ平和を具体化するために欠かすことのできない作業でもあるということです。江戸期の日本人は泰平の世であるにもかかわらず、武道の稽古をし、学歴社会でもないのに学問をし、さらに武士は常に死を思うこと(memento mori)を訓練されていました。彼らは常に武具を身近に置き、それを魂とよぶことによって、武器が単なる道具や手段ではなく、いかなる目的で、いかに正しく用いるのか、という価値と共にあることを意識してきました。こうした侍の精神こそが泰平を維持し、列強の植民地化に直ちに対応する能力を培ってきたのではないでしょうか。武士道こそは悪しき平和でなく、善き平和のために戦う気概をもつ精神性をもっていたといえるでしょう。善き平和は戦時や有事を忘れては達成できないものです。 顧れば戦後日本の平和論は、目的なき経済成長路線とこの点でまったく類似の構造をもってきたといえるでしょう。繁栄は我々に多くの善きものを与えてくれる機会を提供するが、一体それによって我々は何を得るべきなのか、この目的はほとんど考えられることはありませんでした。この繁栄が極点に達したとき、人々は目的を探求することよりも手段を価値そのもののと誤認し、数々の見苦しい行ないをしてきました。この意味に於いても我々は精神性を失ってきたといえます。平和そのものも、金銭そのものも究極価値ではありえないにもかかわらず、それを究極価値と誤認し、閉塞状態に陥っているというのが現在の日本です。平和でありさえすればよい、という心情は、金さえあればよいという心情と相通じるものといえましょう。この二つの過ちは戦後民主主義を支えてきた車の両輪といえます。我々は繁栄の意味を知るためには窮乏を知ることが必要であるように、平和の意味を知るために戦時を知り、それへの覚悟をもつことが必要です。それが平和と富とを正しく統一的に方向づけることになるでしょう。 それでは我々は何のために戦うのか、その目的は何か、この問題を一語で答えることができるなら、我々の世界に政治も哲学も必要ないでしょう。形式論やマニュアルはない、ということだけは確かです。これは個人にとっても一生の課題であり、国家にとっても永遠の課題です。しかし我々は江戸期の武士と同様にそれを意識し続けることによってあるべき平和への道筋を考えることができ、いかに生くべきかを考えられるようになるはずです。我々、こうした観点から有事を想定し、準備することによって我が国のある べき道筋と平和を考えなければいけない。 |
|
From : Kenzo Yamaoka Date : 2002.07.21 13:49 Sub : 国家観 |
小泉首相に対してよく考えて見ると、欠落症状がみられることを指摘しておかなくてはならない。端的な例が、中国・瀋陽総領事館の亡命者連行事件について、事件のあった当夜のコメントである。小泉首相は「冷静、慎重な調査」「日中関係を阻害しないよう」としか発言しなかったのである。私は顔を赤らめて怒る姿を想像していた。 本当に落胆してしまった。 この事件の核心は、中国側武装警察がウィーン条約の「不可侵権」に反して総領事館の 敷地内に侵入し、亡命一家五人を強制連行した点にある。日本の主権が侵害されたという一点を、国の政治指導者が語れないというのはどう理解すべきなのか。その後、日本側の対応が後手に回ったのは、この首相コメントから発しているといって過言ではないように思える。 そこで、「国家観」が日本政治の最大の課題として浮上していく可能性が見えてくるのである。 それが、石原慎太郎氏への待望論につながっているという側面を見逃すわけにはいかない。反米派のようにいわれている石原氏だが、その本質は、日本国家の立て直しにある。 石原氏は産経新聞に毎月一回、「日本よ」と題する論文を寄稿している。そのタイトルのあとには、「国家たれ」という表現が隠されているのである。 現時点では国政復帰の意欲を否定する石原氏だが、都庁幹部の一人は「都政に対する関心が急速に薄れているように見える。銀行課税(外形標準課税)の敗訴も大きかったようだ。四月の登庁日は週に二回ぐらいだった」などと明かすのである。 石原氏の国政復帰シナリオはさまざまに想定されているが、最も可能性の高いのは、来年四月の統一地方選と衆院解散・総選挙が重なるという展開になった場合であろう。石原氏としては都政放棄のそしりを受けずに転身できることになる。石原新党を結成すれば、全国で大量の立候補希望者が集まるのは容易に想像できる。中選挙区制の時代には公認漏れでも強引に出馬できたが、小選挙区制になってそうした道が閉ざされ、政治家志望組の不満が高まっているのである。 石原氏自身は東京の比例一位でなんなく当選可能だ。石原新党が一定の人数を確保できれば、選挙後、ダイナミックな政界再編の引き金になる。石原新党としては自民党側、民主党側のいずれとの組み合わせも可能であるはずだ。自由党、保守党などの動きも重なって、石原新党が加われば過半数を制するという構図になれば、石原政権誕生となる。 あるいは、自民党のことだからそうした展開が予想される事態になれば、機先を制して石原氏を自民党総裁に迎えるという手もあろう。 小泉首相が厳しい政権運営に直面しているのは事実だが、かといって、ただちに「ポスト小泉」を自民党内で探すのは困難な情勢である。 古賀誠前幹事長は、当選七回組の麻生太郎、平沼赳夫、高村正彦の三氏をYKKに次ぐニュー・トリオとして売り出そうとしているが、現段階では成功しているとはいえない。 「次」がいないという現実が小泉政権延命論の重要な根拠になっている。だが、逆にいえ、小泉政権が万一倒れたときには石原氏が登場すれば、ほかの首相候補を一掃する迫力を有するのは間違いないということになるのである。 (一部産経新聞から抜粋しました。) |
|
From : 山岡 兼三 Date : 2002.07.21 13:41 Sub : 道路公団民営化の問題点 |
民営化の世論が強いこと、そして政治家はその世論を無視出来なくなってきているかのような雰囲気を醸し出し、民営化することが如何にも良いことのように番組を構成しているのが目につく。そこでは本質的な問題、すなわち高速道路有料制の是非については何ら議論されず、民営化すれば高速料金が少しは安くなるという極めて矮小化されたレベルで議論されているに過ぎない。 高速道路有料制の問題点を整理してみる。 1)日本の輸送・物流コスト高の主因であること。走行距離500Km(東京-大阪間程度)を例にとれば、日本では高速料金1万円とガソリン代が5千円の計1万5千円がか かるのに対し、アメリカではガソリン代のみの1千5百円程度で、その差が10倍にも及んでいる。 2)高速道路の渋滞による経済的損失は一説には年間12兆円とも言われているが、料金所の存在がその渋滞の主たる原因の一つであること。 3)高速道路サービスエリアの質が悪く料金が高いこと。これはエリア内で営業する業者の参入障害があることと、利用者が高速料金を余分に払いたくないため一般道路に出な いためである。 4)道路公団や道路施設協会そしてそれらの子会社・孫会社の存在を正当化し、官僚等の天下りを許す結果となっていること。 5)高額の高速道路料金の存在が他の交通手段の高料金を正当化していること。 等であり、日本の高速道路問題の本質は、それが日本の高コスト体質の元凶となっていること、及びそれらのために人と物の移動が制限されていることである、と断言出来る。 民営化して上記に指摘したような本質的問題が解決するのだろうか。 答えは全くノーである。民営化の先輩である電力会社やJR各社そしてNTTなどを見ても政府の保護の下、大半が政府(主管官庁)の言いなりになっている。政府が景気対策として公共投資や設備投資を増やす政策を出せば、電力会社などは採算や必要性を無視して巨額の投資を行っているのである。以前に比べれば料金が安くなったものもあるが、それは僅かで諸外国と比べれば極めて高い料金を我々は払わされ続けている。 ましてや高速道路といえども道路である。発展途上国は別として諸外国で日本のように全国に渡って高速道路を有料にしている国があるだろうか。イギリス・ドイツ・オーストラリア等は全て無料だし、フランスやアメリカにおいても料金を取っている道路はごく一部しかない。海外からのお客さんを成田に迎えに行って、何回も料金所で車を止められ料金を払わなければならなくて、恥かしい思いをしたことがあるのは私だけではないだろう。海外のお客さんの方も、迎えに来てくれた日本人が異常な程のコストと時間を費やしているのを見て、気後れしたり日本での商売のやり難くさを感じているのである。 料金の高さ及び料金所の多さは、日本が‘後進国’であることの象徴なのである。 昨年度の道路公団の通行料収入は約1兆9千億円である。一方、借入金の支払利息は約2兆3千億円である。全通行料収入で支払利息すら賄えない状況である。これは96年3月末現在で22兆円以上にものぼる借金をかかえているからである。(詳しくは、週刊東洋経済1月25日号「道路特定財源が生む非常識」を参照) 世界に類のない高額の通行料金を取りながら、借金が膨らむ一方で金利すらも払えないというのは、道路建設を食い物にする政・官・業の存在や、建設行政と道路公団ファミリーそのものに根本的な問題があるとしか考えられない。 日本道路公団を日本道路株式会社に変えたとしても、この根本問題が解決される訳ではない。それは、現在すでに22兆円を越えている借金を切り離し、第二の国鉄清算事業団を作るだけなのである。 また、民営化することの本当の意味は、高速道路料金を永久に徴収すること、そして政・官・業がその有料道路を永久に食い物にしようとすることなのである。 道路整備のための税金は、97年度の税収見積りで、少し古い資料で申し訳ないが、 揮発油税 2兆6130億円 もある。 これだけの税金があれば必要な道路は作れる筈である。足らなければ無駄な道路建設を止めて足りるようにすべきである。新規の道路がなければ生活出来ない人など日本国中どこにもいないのだから。 道路公団が現在かかえている借金は、まず第一に政府が徹底的な行政改革を行って、そこで浮いた資金で返済すべきだろう。第二には道路建設が減ることになるが、上記の道路財源の一定割合をその債務の返済に回すことだろう。そして、それでも借金が残るなら国有財産を処分して返済すべきと考える。 百歩譲って、現在の通行料金収入分にあたる金額を別な形で国民に負担してもらうよう政府が求めることになったとしても、道路公団や料金所は廃止しなければならない。 日本には現在、乗用車や貨物車・商用車を合わせれば約7千万台の自動車がある。通行料金の合計1兆9千億円の収入(料金徴収のための人件費等の巨額の管理費がこの中に含まれているため本当の収入はこれよりも少ないが)を穴埋めするために、それを自動車税として上乗せしたとしても、車1台当たり年間2万7千円程度である。 地域により高速道路の整備状況に差があり、また利用頻度も違うので、この自動車税は市町村税とし地域ごとに格差をつければ不公平感はなくなるのではないだろうか。 いずれにしても道路公団と料金所を廃止して、無駄と腐敗の大本を断たなければならないまた、この有料道路制廃止こそが日本経済に対するこれ以上もない最大の景気対策と言えるのではないだろうか。 道路公団民営化を唱える人たちは、現状の既得権者で行政改革を骨抜きにしようとしている人たちであることを肝に命じ、騙されないようにしなければならないと考える。 民営と云うには資本主義原理であり、お互いに競争して消費者にサービスすることである。しかしながら東北新幹線 東海新幹線にしても競争する相手がいない、道路でも東名 関越 東北道 にしても他社がいない。航空会社は同じ路線を航空会社どうし競争し航空運 賃を安くする努力をしている。道路公団が民営化されて国民は得をするのか。最初首都高を造ったとき、最後は料金は無料になると云っていた。東名でも安くなると、国民には説明していた。可笑しいではないですか?何時もご返事くれませんね。民営の独占で料金は安くなりません。無料にすれば相乗効果は期待でき、JRも運賃値下げしなければならないでしょう。海外援助の金を回したら如何ですか? |